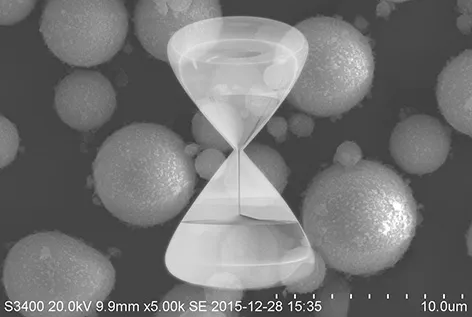ゴムや特定のプラスチック製品の製造においては、 カーボンブラックの細かさ は重要な要素です。製品の性能とコストの両方に影響します。しかし、業界では粉砕粒度の選択において「細かければ細かいほど良い」という単一の基準に固執しているわけではありません。むしろ、最終的な用途シナリオに基づいて適切な粒子径の範囲を決定する必要があります。理想的には、廃タイヤ熱分解から得られるカーボンブラックの粉砕の目標は、一次粒子径(約 325~800メッシュ)と良好な分散性を確保します。しかし実際には、製品の性能要件、生産コスト、そして加工の難しさのバランスを取り、これら3つの要素の間で最適な均衡点を見つける必要があります。

ファインカーボンブラックの利点
微細カーボンブラックにはいくつかの利点があります。
まず、補強性能を大幅に向上させることができます。これは、ゴム業界が細さを重視する主な理由です。補強は表面積に依存します。 より小さな粒子 表面積が広くなるため、ゴム分子との接触点が増え、結合力が強くなります。その結果、引張強度、引裂強度、耐摩耗性が向上します。
第二に、インク、コーティング、プラスチックなどの着色用途では、より細かいカーボンブラックにより、黒度が高まり、青みがかった色合いになり、着色力が強くなり、隠蔽力が優れています。
最後に、理論的には、一次粒子が小さいほど材料マトリックス内に均一に分散しやすくなり、粒子の凝集によって引き起こされる欠陥が低減し、製品の品質安定性が確保されます。
過剰研磨の欠点

しかし、カーボンブラックの粉砕は単に「細かくすればするほど良い」というものではありません。過剰に粉砕すると、次のような複数の欠点が生じる可能性があります。
- エネルギーとコストが急激に上昇します。 ミクロンからナノスケールまでの粉砕には多大なエネルギーが必要です。粒子が細かくなるほど、コストも高くなります。
- 悪化した集積 – 粒子が細かいほど表面エネルギーが高く、容易に二次クラスターに再凝集します。これらのクラスターは分散しにくく、微粒子化の利点が打ち消されてしまいます。
- 処理が難しくなる – ゴムの場合、非常に微細なカーボンブラックは粘度を高めます。混合が困難になり、エネルギー消費量が増加します。加硫速度も低下する可能性があります。プラスチックの場合、過剰な添加は溶融強度を低下させ、成形に影響を及ぼす可能性があります。
- パフォーマンスの過剰とコストの無駄 – 着色セメントレンガや必要量の少ないプラスチック充填剤などの低品質の用途では、微細カーボンブラックは不要であり、無駄につながります。
- 潜在的な構造的損傷 – 過度に粉砕すると、カーボンブラックの骨材の形態が損なわれ、固有の強化特性が弱まる可能性があります。
用途に応じた粉砕粒度の選択
高級ゴム製品(タイヤ、コンベアベルト): 500~800メッシュ、骨材サイズに近く、表面積とDBP油吸収値を厳密に制御します。
中低価格帯ゴム製品(サイドウォール、ソール、インナーチューブ): 約 425 メッシュ、性能、コスト、加工性のバランスが取れています。
プラスチックマスターバッチ、コーティング、インク: 約500メッシュ、着色力と分散性に優れています。
低価値充填用途(コンクリート、トラック、舗装用レンガ): 約80メッシュの粗粉末でコストを最小限に抑えます。
結論
要約すると、廃タイヤ由来の熱分解カーボンブラックには「最適な粒子径範囲」があり、これは対象用途によって決まります。盲目的に極小粒度を追求すると、生産コストとエネルギー消費量が増加するだけでなく、凝集、処理上の課題、性能低下を引き起こす可能性があります。科学的なアプローチは、実験的試験を実施し、性能要件を満たす最も経済的で適切な粉砕粒度を特定することです。